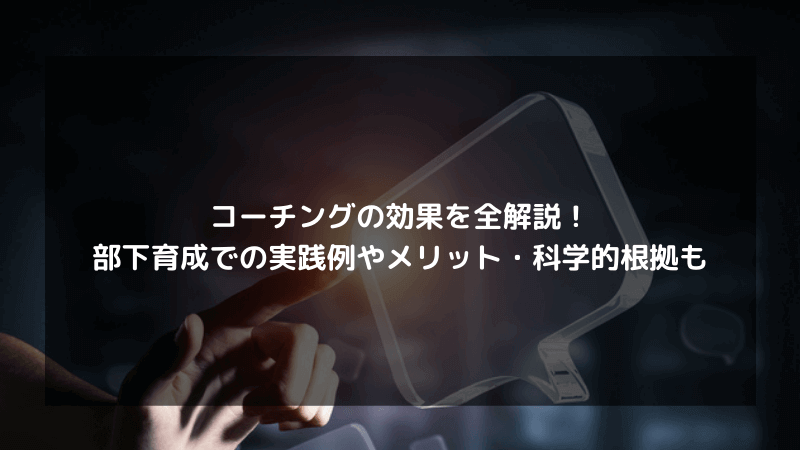
COACHING DOJO編集部
2021.03.30 / 32 min read

この記事の監修者
濱崎 翔吾(銀座コーチングスクール認定コーチ)
東京大学経済学部経営学科。心理学や心理療法、チームビルディングなどについて学ぶ。スタートアップ数社でのインターン経験、Youtubeでの情報発信経験を経て、ステラー株式会社にジョイン。現在はコーチングを通して多くのクライアントの目標達成を支援している。
コーチングの真価をわかりやすく伝え、みなさんのコーチングとの”出会いの場”を創出いたします。
効果的な部下育成の方法として多くのビジネスシーンで取り入れられてきている「コーチング」。
「部下育成にコーチングを取り入れると、どんなメリットがあるの?」や「コーチングはどんな場面で行えばいい?」、「本当に効果はある?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、部下育成・人材全般のそれぞれにおけるコーチングの効果を徹底解説します。
認定コーチの資格を持つ筆者の立場から、コーチングのメリットやデメリット・科学的根拠をご紹介するので、あなた自身がコーチングを取り入れる理由や目的がはっきりするでしょう。
最後にはコーチングの学び方もご紹介するので、あなたにぴったりの形で、コーチング学習のスタートが切れるはずです。
コーチングを効果的に取り入れて、部下育成と自己実現を加速させましょう!
コーチングの意味
COACHING Training Planning Learning education Coaching Business communication man of business knowledge
そもそもコーチングとはどのような意味なのでしょうか。
他の言葉との比較や、代表的なコーチングスキルを参考にしながら、コーチングという言葉の輪郭を少しずつ掴んでいきましょう。
コーチングとティーチングの違い
コーチングと似た意味を持つ言葉に「ティーチング」という言葉があります。
コーチングとティーチングは研修会や参考書でもよく引き合いに出され、比較されています。具体的な違いは何か、それぞれどんな場面で使えば良いのか疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?
2つの言葉の意味を掘り下げ、違いを明確にしていきましょう。
コーチングとは
実は「コーチング」という言葉に世界共通で通用する明確な定義はありません。
団体や取り組む上での思想によって少しずつ違うので、コーチングを定義している団体の文章をいくつかご紹介します。
思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通して、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くこと
国際コーチング連盟(ICF)
コーチングとは、問いかけをベースとした対話によってクライアント(相談者)の目標達成や問題の解決をサポートするコミュニケーション方法
一般社団法人日本コミュニケーショントレーナー協会
コーチングは、「人が本来もっている能力を最大限に引き出し、可能性を大きく拓かせることを目的とするコミュニケーションの体系」である
菅原 秀幸(2013) アカデミック・コーチングによる大学教育変革の試み:ティーチング主体型講義からコーチング主体型講義への進化 開発論集 第92号 1-13貢
いずれも少し固い表現で紹介されていますが、共通しているのはコーチングとはクライアントの目的達成をサポートする手法である点です。しかし、コーチはクライアントの考えや行動に制限を加えたり、強制したりすることはありません。
コーチングを用いる上での共通理解として、課題に対する答えや次に向けての発想はすべてクライアントの中にあると考えます。
コーチングはコーチとクライアントが1対1の関係であるという前提で考えられています。目的達成を目指す上で、クライアントが自ら考えや思いを言葉にして表すため、双方向のコミュニケーションを行うことがとても重要です。
コーチングとは、コーチとクライアント間で行われるコミュニケーションスキルであるともいえます。対話を経て、クライアントが自身の変化や成長を実感できる環境を整えていくことが、コーチには求められているのです。
コーチングの意味についてさらに詳しく学びたい方は、「これだけ読めば分かる!コーチングの意味をメリット・種類・スキルから解説」の記事を参考にしてください。
※ちなみにCOACHING DOJOでは、LINE@登録で”パーソナルコーチング”サービスを初回完全無料でご提供しております。
その他コーチングに関するダイジェストも随時更新しております。
ティーチングとは
先生を英語でティーチャー(teacher)と呼ぶように、ティーチングとはすでにある答えをクライアントに教えることです。
手法もコーチングと異なる点がありますが、最大の違いは、ティーチングでは教える立場にいる人が正解を持っている点です。
ティーチングでの目的は正解をクライアントに伝えることです。さらに、コーチングは1対1の関係を基本として考えますが、ティーチングでは1対多数を想定しています。
答えを持っていない人に、変わることない答えを授けるため、ティーチングは一方通行のコミュニケーションと考えることができます。日本の学校教育はまさにティーチングで成り立っているかもしれませんね。
大勢に情報を素早く伝達するにはティーチング効果を発揮し、1度作った資料や素材も繰り返し使うことができるため、効率が非常に高いです。
ビジネスコーチング時の「アドバイス」に関して今日も訊ねられた。過度なアドバイスはティーチングモードになりかねないが、適切なアドバイスは重要と考える。大切なのはタイミング。
相手が受け取れる体勢になってから行う。いきなり伝えるよりも一言許可を取ってからの方が効果的な事が多い。
— 染屋 光宏 / 多彩なコーチングを通じて人と組織の成長に貢献する。 (@Soulvision_Jpn) November 30, 2020
コーチングとティーチングの違いについてさらに詳しく学びたい方は、「なぜあなたの部下は育たない?ティーチング・コーチングの違いと使い分け」の記事を参考にしてください。
※ちなみにCOACHING DOJOでは、LINE@登録で”パーソナルコーチング”サービスを初回完全無料でご提供しております。
その他コーチングに関するダイジェストも随時更新しております。
代表的な5つのコーチングスキル
コーチングとティーチングの違いについて整理したところで、次はコーチングで用いる基本的なスキルについてご紹介します。
コーチングには以下の5つの代表的なスキルがあります。
- 認める
- 聴く
- 質問する
- フィードバックする
- リクエストする
それぞれの特徴を理解し、コーチングスキルをより高めていきましょう。
認める
コーチングを行う上で、クライアントとの信頼関係の構築は、コーチングの成果を高めるためにも非常に重要な要素となります。
クライアントが迷っていたり、本筋から少しズレた考えを持っていたとしても、まずは認めてあげることが必要です。
「承認」とも呼ばれますが、クライアントは認めてもらっている実感を持つことで、安心感を感じより本音が引き出しやすくなります。
「認める」ときの注意点としては、コーチは反論や判断をしないということです。
認めることの目的は、クライアントに安心し、自身のことをより話してもらうためです。
たとえば、上司に相談を持ちかけたとき「そうは思わない」と反論されたら、部下はどう感じるでしょうか。
また、反論がないとしても、「それは正しい」や「それは間違っている」といった判断を付けられてしまうと、部下は正解を探してしまいます。
個人の価値観による正否の判断はその先の発展の芽を摘んでしまう可能性があります。
部下も上司に否定されるかもしれないと思ってしまうと、本音で話せる関係性とは言えません。
とはいえ、すべての発言や発想を正しいものとして受け入れる必要はありません。
中には反論しせずにはいられないものや、判断を付けたくなるような発言も出てくるでしょう。
当人が感じ、思ったことを尊重し、受け止めてあげるという意識を持ってコミュニケーションを図っていきましょう。
聴く
コーチングスキルにおける「聴く」とは相手の話に心を集中させて聴くことを意味します。
教育業界には「傾聴」という言葉があるのですが、ご存知の方はイメージのしやすいスキルだと思います。
聴くスキルの目的は、「相手にストレスなくたくさん話してもらう」ことです。
具体的な振る舞いとしては以下のものが聴くスキルに分類されます。
- ペーシング
- 要約する
- 言い換える
- 沈黙する
- 「それから?」や「その他には?」といった投げかけをする
1つずつ内容を見ていきましょう。
・ペーシング
ペーシングとは、話すスピードや声の調子、姿勢などを相手に合わせるというスキルです。「ミラーリング」と呼ばれることもありますね。
・要約する・言い換える
要約と言い換えは非常によく似ているスキルです。
脈略なく、ただひたすら語ってくれた内容をまとめたり、別の表現や言葉を用いることで、クライアントの充足感が上がっていきます。
・沈黙する
沈黙が聴くスキルに分類されることに違和感を感じた方もいるのではないでしょうか。
立場に差のある関係の会話では、時として、上に立つものの発言が多くなってしますことがあります。誰もが発言しやすい環境を作るためにも、沈黙することは重要になってくるのです。
・「それから?」や「その他には?」といった投げかけをする
クライアントが最初に口にする意見や、考えは十分にまとまり切っておらず、本音の意見ではないこともあります。
コーチはクライアントの最初の発言を足がかりにし、思考を促す発問を続けることで、より明確にクライアントの考えや思いを知ることができるのです。
質問する
クライアントに質問をする目的は相手の中にある答えを引き出すことです。まだ経験が浅い中での考えを具体的にするためには、質問を重ねながら、頭の中を整理していく必要があります。
質問のやり方には以下の2つがあります。
・オープンクエスチョン
・5W1H
オープンクエスチョンとは「はい」や「いいえ」では答えることのできない質問のことを指します。「目標を実現したいですか?」といった質問は「はい」か「いいえ」で答えることができてしまうため、クローズド・クエスチョンと呼ばれます。
オープンクエスチョンでは「何を達成したいですか?」や「どのように進んでいきたいですか?」と質問します。回答に幅を持たせることで、クライアントは自由に回答できるようになり、新たな発想や視点が生まれやすくなります。
また、質問を重ねるときには5W1Hを意識するとより効果的です。
5W1HとはWhen(いつ)・Where(どこで)・What(何を)・Who(誰と)・Why(なぜ)・How(どのように)の英語の疑問文で使う単語5つの総称です。クライアントにより具体的に考えを深めてもらうためにも、発問は5W1Hから始まるとよいでしょう。
先程の例でも「何を(What)」や「どのように(How)」と切り出していますよね。
質問スキルを使うときの注意点としては、誘導尋問にならないようにすることです。
コーチはあくまで目的にたどり着くまでのサポート役です。1つ1つの判断や決定はクライアントがするものです。
コーチが進んでほしいと思う方向に意識的に誘導することは、当然避けることですが、意識せずとも寄ってしまうこともあります。誘導尋問にならないよう、「認める」ことや「聴く」ことを忘れずにしていきましょう。
フィードバックする
フィードバックとは、相手の考えや意見を聴き、感じたことや思ったことをそのまま相手に伝えることです。結果に対する振り返りや反省とは意味合いが異なりますので、ご注意ください。
フィードバックの目的は、クライアントに気付きを促すことです。「私にはあなたが〜のように見えます。」や「私には君が〜なったように思うよ。」というようにコーチの主観による印象を伝えます。
クライアントは他者から見た自身の印象を受けることで、気付かなかった変化や成長を感じ、さらに成長していくきっかけとなるのです。
フィードバックをする際には決めつけや押し付けにならないよう注意しましょう。「あなたはこう思っているでしょう。」や「これがやりたいんだね。」といった発言はクライアントの反発を生んでしまうかもしれません。
主語は「私は〜」から始まる伝え方が望ましいでしょう。
リクエストする
コーチングスキルでの「リクエスト」とはクライアントに行動を要求することを意味します。
ただ要求するのではなく、期待や応援の言葉が入ると、クライアントのモチベーションにも強く影響し、ポジティブに取り組むことができます。
さらに発展させた技術としては、クライアントの現在の能力では少し難しい課題を要求するというものがあります。当然最初のうちは困難が多くなることが予想されますが、お互いが気付いていない潜在能力を引き出す機会につながるかもしれません。
あるコーチのハーフタイムを聞いていたら以下の順番で子供達に話をしていた。①できていることを褒める②改善点や課題を伝える③挑戦を促す力強い言葉で送り出す
素晴らしいなと思った。聞いている僕のモチベーションが上がりました。自分も試合に出場したくなりましたね。
— 後藤雄治/YujiGoto (@gotolab2) September 8, 2020
コーチングのスキルについてさらに詳しく学びたい方は、「【実践】基本のコーチングスキル5つと、部下育成に取り入れる秘訣を紹介!」の記事を参考にしてください。
※ちなみにCOACHING DOJOでは、LINE@登録で”パーソナルコーチング”サービスを初回完全無料でご提供しております。
その他コーチングに関するダイジェストも随時更新しております。
コーチングの実践形式3パターン
Two diverse business coaches making flip chart presentation at meeting, smiling businesswoman mentor using computer tablet, presenting project strategy, financial report, marketing plan at briefing
コーチングスキルを確認したので、具体的な実践形式のパターンを見ていきましょう。
クライアントの性質や、属している団体によってコーチングの種類も変わってくるので、ぜひ実践の際の参考にしてみてください。
ビジネスコーチング
ビジネスコーチングとは、「ビジネス領域に特化したコーチング」の事を指します。しかし、一言に「ビジネスコーチング」といってもビジネスの幅は広がり続けているので、捉える枠が広すぎるかもしれません。
ビジネスコーチングと呼ばれているものの一例をご紹介しましょう。
- 仕事上の成功をテーマにしたコーチング
- やりたいことや転職をテーマにしたコーチング
- 経営者向けのエグゼクティブコーチング
- 経営層を育成するために受けさせるエグゼクティブコーチング
- マネージャーがコーチングを取得し、部下育成に生かすこと
管理職やマネージャー・人事担当の職に就き、会社全体の部下育成に取り組みたいのであれば、
「会社がマネージャーにコーチングを学ばせること、部下育成能力を引き上げること」
が適切なビジネスコーチングかもしれません。
自分自身の部下育成能力を伸ばしたい場合は、
「マネージャーがコーチングを学び、部下育成に用いていく」
ビジネスコーチングの形が適しているかもしれません。
コーチングを学び取り入れていく際には誰が、何を目的として取り組むのかをその都度明確にしていく必要があります。
ビジネスコーチングについてさらに詳しく学びたい方は、「ビジネスコーチングで部下育成が変わる|導入時のコツや注意点・成功事例」の記事を参考にしてください。
※ちなみにCOACHING DOJOでは、LINE@登録で”パーソナルコーチング”サービスを初回完全無料でご提供しております。
その他コーチングに関するダイジェストも随時更新しております。
職場でのコーチングの実践例
実際には部下にどのような声かけや発問ができると、コーチングとして効果的なのでしょうか。
コーチング基本的に、
目標設定→現状確認→目標達成までの過程の設定→行動の決定
といった流れで進んでいきます。
そして、1度サイクルが終わった後、コーチからクライアントに
- 「何がうまくいった/うまくいかなかった」
- 「うまくいった/いかなかった理由は何か」
- 「今回の取り組みで、どんな学びを得たか」
というように、様々な角度から発問を重ね、クライアントの気付きや学びを深めていくことになります。
パーソナルコーチング
パーソナルコーチングとは専属のコーチとクライアントが1対1 で受けるコーチングのことです。
コーチがクライアント1人に専門で対応するので、細かいところまでコーチングを通して入り込んでいくことができます。また、自分の考えや思いを専属コーチ1人に、正確に伝える必要があるため、コミュニケーション能力や表現力の向上が期待されます。
セルフコーチング
セルフコーチングとは、自らがコーチとなり、自分自身を目標達成へと導いていくコーチング手法です。
自分がコーチですので、他人に依頼するためのコストや、心理的な障壁がなく始めることができるのが特徴です。また、時間や場所を選ばず取り組めるのもメリットの1つといえるでしょう。
しかし、踏み出すきっかけも自分で用意する必要があります。時間や場所が指定されていないがゆえに、後回しなりがちになってしまうのもまた事実。
コーチングに対する正しい理解をもとに、継続して取り組めば、通常以上のスピードで目標達成につながることが期待されています。
コーチングを部下育成に取り入れるメリット
Office Secretary, Business Woman Listening to Speaking Business Man, Coacher at Big Monitor with Puzzle Pieces and Graphs. Employees Watching Presentation. Cartoon Characters. Flat Vector Illustration
ではコーチングを部下育成に用いると具体的にどのようなメリットがるのでしょうか?
現状で成果が見えないと悩んでいる方も、継続していれば効果は期待できますので、これからご紹介する姿を想像し続けていきましょう。
自立型人材が育成できる
コーチングにより、行動を自発的に行う人材を育成することができます。
答えを与えられるのではなく、自ら導き出し挑戦していく経験を重ねた人材は、主体的に取り組むことが当たり前になっていきます。
また、何かトラブルや予期せぬ事態が起きた際でも、慌てることなく対応できるようになるでしょう。上からの命令や指示のみで動かしていると、人は考える事をやめてしまいます。
組織としても、現在よりさらに成長するため、自立型人材の育成は欠く事のできない要素となっているのです。
生産性が上がる
同じ組織に属している人でも仕事上で直接の関わりがないと、何をしているのかや、何を考えているのかを把握することはできません。
コーチングには双方向のコミュニケーションが必要不可欠となっています。導入により、コミュニケーションの頻度が増え、徐々に組織内にもコミュニケーションの輪が広がっていきます。
お互いのことを理解することで、業務の分担や、工数の削減ができるようになり、全体の生産性の向上につなげることができます。
部下の強みや可能性を引き出せる
コーチングを通してそれぞれの考えや視点を引き出せるようになると、誰にはどんな作業が向いているのかわかるようになります。
組織では営業が得意な人もいれば、書類作成やデータ管理が得意な人、皆それぞれ何か強みを持っているはずです。
しかし適性を見出そうとせず、頭数をそろえるためだけに配置をしてしまうと、生産性が上がることはありません。不得意な分野に配置されてしまったことにより、クライアントのモチベーションも低くなっていってしまうでしょう。
適性を見分けるにはある程度の期間を必要とします。コーチングを適切に行い、初期段階で適性を見出し、お互いにポジティブに仕事に向かえる環境を作り上げていきましょう。
コーチングを部下育成に取り入れるデメリット
Confident business coach. Corporate coaching. Team of company professionals posing with arms crossed. Copy space on grey background.
ここまでコーチングの効果やメリットについてご紹介を重ねてきましたが、コーチングも万能の道具ではありません。
デメリットも理解し、他の指導法とうまく使い分けていきましょう。
一斉に教育できなくなる
コーチングの大きな特徴は基本的に1対1を想定しているということです。
裏を返せば、コーチングでは1対多数を想定し切れていません。
仕事に取り組んでいく上で、全員に必ず知っておいて欲しい情報や、新しい事柄の周知にコーチングは適しているとは言えません。
上司にコーチングスキルや能力が求められる
コーチングを効果的に行うには、コーチに正しい知識と確かなスキルが求められます。
しかし、コーチングのスキルは数学の公式のように一旦覚えてしまえば、すぐに使うことができるようになるものではありません。
まず、コーチングスキルの理解に時間を要します。今までとは違う新しい取り組みに、上司も挑戦するのですから当然と言えば当然ですが、精神的にも肉体的も負担がかかります。
また、筆者の経験からも仮に理論を完璧に理解したとしても、残念ですが意味のないこともあります。現場では学んだ理論が全く役に立たないなんてことはコーチングの現場ではよくあることなのです。
学んだだけではなく、上司自身もコーチングの経験を積み重ね、成長していく期間が必要となるのです。
効果が出るまで時間がかかる
コーチングは1日2日で効果がすぐに出るものではありません。1度話をしっかり聴いたから大丈夫や、目標をリクエストしたから伸びるなんてことはありません。
コーチングには継続が必要です。人によって必要となる期間は異なります。3ヶ月で効果が目に見えるようになる人もいれば、1年が必要な人もいるでしょう。
効果が実感できないのはコーチングが有効に働いていないわけではなく、まだエネルギーを溜めている状態であると言えます。
コーチも粘り強くコーチングを続けていく必要があるのです。
人生全般でのコーチングのメリット
A man running up to the hand drawn stairs as a concept of coaching, business training, goal achievment, success, progress, carreer ladder, pinkish coral blue palette. Vector illustration on white background.
コーチングを受けることで得ることできるメリットは、ビジネスやスポーツの分野に限ったことではありません。何気ない日常においても、コーチングを受けたことによる変化を実感し、生活をより豊かなものにしていくことはできるのです。
目標とすることはダイエットでも、勉強習慣でも構いません。
なかなか1人では達成が難しいと感じることでも、コーチとともに歩むことで、達成の難易度を下げることができます。コーチングを受けることにより、今までの視点よりもさらに広く、そして深く考えを巡らせていくことができるようになります。
新しい視点を持つことで、考え方も日々変化し、行動も変わっていきます。行動を変えることができれば、その先にある「理想とする自分」に近づくことができているといえるでしょう。
また、コーチングを受け、成果や効果を実感し変化をフィードバックしてもらうことで、モチベーションの維持にもつながります。
科学的に証明されたコーチングの成果
Start up partners are working in casual clothes, discussing the ideas for new strategy of development.
コーチングには様々なメリットがあるとご紹介してきましたが、今までの効果は何も机上の空論ではありません。コーチングの効果については学術的にも証明されているので、どのような変化が見られたのかも含め、いくつか見ていきましょう。
LS Green, LG Oades and AM Grantらが2006年に28名に対し、10週間コーチングを実施し、その成果について研究しました。
結果は
- 目標達成に向けて努力する度合い
- 目標達成が実現できると期待する度合い
- 幸福度
の3つが、コーチングを行わなかったグループと比較して、上昇が見られました。
そして、コーチングを受けたグループの効果は実験後、30週が経過しても継続していたそうです。
3つの項目の中で「幸福度」以外の項目については、コーチングにより向上することは想像しやすいと思います。しかし「幸福度」だけ、曖昧な表現で具体的なイメージが掴みづらいかもしれません。
今回は「幸福度」について、研究結果も踏まえながらもう少し掘り下げていきましょう。
幸福度が上がる
ハーバード大学のローランド・フライヤー教授が幸福度に関して行った実感があります。
子どもを
A:テストで良い点をとればご褒美をあげる
B:本を一冊読んだらご褒美をあげる
の2つのグループに分け、どちらが学力テストの結果が上がったのかを調べました。
結果はBグループの結果が上がりました。Aグループには改善が全く見られなかったそうです。
理由としては、Aグループはご褒美をもらう条件がBグループより難しいため、ご褒美をもらった回数に大きな差が出たことが考えられます。
Bグループはご褒美をもらうために取り組めばいいことが明確であるということも、大きな要因と言えるでしょう。「褒めて伸ばす」という言葉がありますが、人間は誰かから認められ、期待されているとこ心の充足感が上がります。
精神的に満たされている状態を保つことができるということも、コーチングの1つの効果になるのです。
ビジネス上の成果が上がる
ビジネスにおける成果についても、研究がなされ、その効果について明らかにされています。
国際コーチ連盟(ICF)は「企業のコーチングに対するROI(投資利益率)」というテーマで調査を行っています。
ROIとは行った投資でどれだけの利益を上げることができたのか知ることできる指標です。
調査結果では、
- 業務のためにコーチを起用した企業は初期投資と比較し、平均的に7倍の効果があった
- コーチをつけた企業のうち、約85% は少なくとも初期投資の100%の効果があった
- クライアントの目標分野に大きな影響を与えた
といった報告がされています。
効果の幅にばらつきがあることは予想されますが、高い確率で効果は期待できるといえるでしょう。
コーチングの手法の学び方
Business school vector, students listening to personal coach showing information on whiteboard. Man wearing formal suit teaching people skills. Website or webpage template, landing page flat style
ここまでご紹介してきましたコーチングに関することは、コーチングのまだほんのごく1部に過ぎません。
本格的なコーチングの理論や手法はどのように学ぶことができるのでしょうか?
方法はいろいろありますので、まずは1番取り組みやすいと感じるものから始めてみてはいかがでしょうか。
コーチング講座で学ぶ
講座でコーチングを学ぶ方法は金銭的に余裕のある方や、本気で取り組みたい方に最も確実な方法です。
プロのコーチ陣からノウハウや、経験談を直接聞くことができる機会は今後のキャリアにおいてとても貴重なものとなるでしょう。
しかし、その分費用や時間はかかってしまいます。最近は動画で学べる講習会などもあり、比較的料金も低くなっているため、動画から始めるというのもいいかもしれません。
本で学ぶ
気軽にコーチングに触れてみたいや、話題になっているから少し興味があるといった方には本から始めるのがオススメです。
1冊買ってしまえば、他にお金はかかりませんし、時間も好きな時間で取り組めるで、入り口にはもってこいかもしれません。
コーチングを受けて学ぶ
直接自分がクライアントとなり、コーチングを実際に受けてみるのも有効な学習方法の1つです。
そもそもコーチングに効果があるのかいまいちわからない、不安だと感じている方にオススメです。プロコーチのスキルを肌で感じ、変化の過程を自分で感じることは、今後のコーチングに必ず役に立ちます。
コーチングの学び方についてさらに詳しく学びたい方は、「コーチングを学ぶ定番の方法3選!本・講座・目的・つまずくポイントを解説」の記事を参考にしてください。
※ちなみにCOACHING DOJOでは、LINE@登録で”パーソナルコーチング”サービスを初回完全無料でご提供しております。
その他コーチングに関するダイジェストも随時更新しております。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
コーチングを取り入れることで、どのような変化が起こるのか。あるいはコーチングの課題はないか整理がついたのではないでしょうか。
活かすことのできる場面の多いコーチングスキルを効果的に使い、組織や個々人の育成につなげていきましょう!
![]()
上昇志向の強い若者のためのコーチング特化メディア「COACHING DOJO」コーチング・マネジメント・自己実現・コミュニケーションなどに関する記事をご紹介します。

